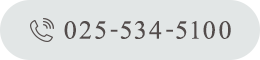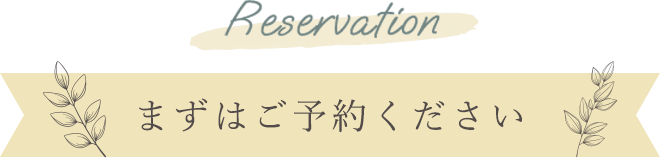- 下痢が続く、下痢が止まらない
- 下痢は出し切った方がいい?
- 下痢とは?シャーシャー便は下痢?
- 下痢症状の受診のタイミング
- 止まらない下痢の原因
- 下痢の診断・検査
- 下痢の治療
- 下痢が続く、下痢が止まらない方へ
下痢が続く、
下痢が止まらない

下痢は、突然腹痛が起こるとともに便意を催し、1日のうちに泥のような便(泥状便)や水っぽい便(水様便)が何度も排泄される状態です。なお、腹部の不快感だけが起こることもあります。
下痢は、便の形状や色などからおおよそ判断できるので、便の状態を確認して診察時に医師までお伝えください。
また、吐き気・嘔吐、脱水症状、発熱などの症状も起こり、その症状が続く場合は早めに当院までご相談ください。特に、血液・粘液が混ざった便が出る、鮮血が混ざった水様便が出る場合、大腸で炎症や潰瘍が発生していることが疑われるため、すぐに当院までご相談ください。
急性下痢
急性下痢は、2週間以内に下痢症状が治まるタイプです。ウイルス・細菌などの感染による急性腸炎の症状として下痢が起こるケース、暴飲暴食や冷えによって下痢が起こるケースに分けられます。原因菌には、ノロウイルスやロタウイルス、O-157などの病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌などが挙げられます。
慢性下痢(3週間以上続いている下痢)
慢性下痢は、下痢症状が3週間以上続くタイプです。代表的な原因には、過敏性腸症候群、大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病などの消化器系の疾患が挙げられます。また、お薬の副作用や過剰なストレスが原因となることもあり、術後の症状として起こることもあります。
下痢は出し切った方がいい?
下痢は辛い症状ですが、出し切る方法はありません。無理に出そうと強くいきむと身体に負担がかかってしまうので、症状が治まるまではお腹を冷やさないように注意し、安静に過ごしてください。
お仕事など生活に影響が出ている場合、早期改善のためにも検査を受けて原因を特定し、原因に応じた治療を受けましょう。
下痢とは?
シャーシャー便は下痢?
下痢とは水っぽい便が何度も出る状態ですが、正確には便の形状や水分量などから判断されます。
形
通常の便はバナナのような形をしていますが、形が崩れた柔らかい便を軟便と呼び、水のようにサラサラした便を下痢便と呼びます。
水分量
便の硬さは大腸での水分の吸収量が影響しています。便の水分量が70~80%の状態が望ましいですが、80~90%になると軟便となり、90%以上となると下痢便になります。
期間
下痢症状の持続期間に応じて急性下痢と慢性下痢に分けられます。急性下痢は2週間以内に落ち着きますが、慢性下痢では3週間以上にわたって下痢症状が続きます。
下痢症状の受診のタイミング
救急対応が必要な下痢
- 下痢便は1時間に1回以上出る
- 鮮血が混ざった下痢便が出る
- 激しい腹痛や高熱(38℃以上)が出る
- 下痢に伴って嘔吐し、水分補給がままならない
消化器内科を受診すべき下痢
- 下痢に伴って腹痛、吐き気や軽い嘔吐症状が起こる
- 下痢が長引いている
- 下痢と便秘を交互に繰り返す
- タール便(黒い便)や粘血便が出る
止まらない下痢の原因
下痢の原因は多岐にわたり、食べ過ぎ・飲み過ぎ、香辛料などの刺激物の摂取、アルコールの過剰摂取、過剰なストレス、お薬の副作用、細菌・ウイルスの感染症。炎症性腸疾患などが挙げられます。下痢は、通常よりも便が大腸を早いスピードで通るため、水分を十分に吸収できないことで発生します。
食中毒・感染性腸炎(細菌やウイルス)
原因菌には、ロタウイルスやノロウイルス、O-157などの病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌などが挙げられます。激しい下痢に伴って、発熱や嘔吐などの症状が現れます。
過敏性腸症候群
潰瘍性大腸炎は、消化器に器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛に伴って便秘と下痢を繰り返す疾患です。はっきりとした原因は分かっていませんが、腸の蠕動運動の低下や自律神経の乱れによって起きていると考えられています。
過敏性腸症候群は、症状に応じて下痢型、便秘型、混合型に分類されます。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に慢性的な炎症が発生し、潰瘍ができる疾患です。主な症状には、腹痛や下痢、血便などが挙げられます。こうした症状が現れる活動期(再燃期)と症状が治まる寛解期を交互に繰り返すことが特徴です。原因や発生機序がはっきりしておらず、完治させる治療法が確立されていないため、厚生労働省から難病指定を受けています。
下痢の診断・検査
問診にて、下痢の状態や起こり始めた時期、頻度、生活習慣などについて詳しくお聞きし、その情報をもとに必要な検査を行います。
急性下痢の場合
食中毒が疑われる場合、細菌やウイルスなどの病原体を突き止めることが必要です。より詳細な問診を実施後、血液検査や検便検査を行います。
慢性下痢の場合
 より詳細な問診を実施後、原因を特定するために大腸カメラ検査や血液検査を実施します。大腸カメラ検査は、大腸粘膜を直接観察でき、怪しい病変があれば組織を採取して、病理検査に回すことで確定診断に繋げられます。大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)は、昨今日本で発症数が増え続けており、進行すると重篤な状態になる恐れがあるため、早期発見・早期治療が欠かせません。
より詳細な問診を実施後、原因を特定するために大腸カメラ検査や血液検査を実施します。大腸カメラ検査は、大腸粘膜を直接観察でき、怪しい病変があれば組織を採取して、病理検査に回すことで確定診断に繋げられます。大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)は、昨今日本で発症数が増え続けており、進行すると重篤な状態になる恐れがあるため、早期発見・早期治療が欠かせません。
下痢の治療
下痢が起きている場合、脱水状態にならないようにこまめに水分を補給しましょう。下痢は急性・慢性にかかわらず、食事管理が重要です。
具体的な治療内容については、次に説明するように急性・慢性で違いがあります。
急性下痢の場合
脱水症状を防ぐため、こまめに水分補給を行ってください。嘔吐などの症状もあり、口から水分を摂取するのが困難な場合は点滴から輸液製剤を体内に投与します。急性下痢では、無理に下痢を押さえようと市販の下痢止めを飲むと病原体を排出できなくなるため、自己判断による服用はお控えください。医師の管理の下で治療を受けましょう。食事は消化しやすいものを少しずつ食べましょう。薬物療法は、抗菌薬や整腸剤を使用します。
慢性下痢の場合
慢性下痢は、何らかの疾患が原因になっている可能性があるため、検査により原因疾患が特定できたら、疾患治療を優先して行います。また、下痢症状を改善するための食事療法も並行して行います。食事は、香辛料などの刺激物や高脂肪食、飲酒は控え、うどんや白粥など柔らかい食べ物、水溶性食物繊維を含むリンゴやバナナなどを食べましょう。下痢の原因がお薬の副作用だった場合、かかりつけ医に相談して処方内容を見直すか、あるいは減薬・休薬などの対応となります。
下痢が続く、
下痢が止まらないは
上越市の小山医院まで
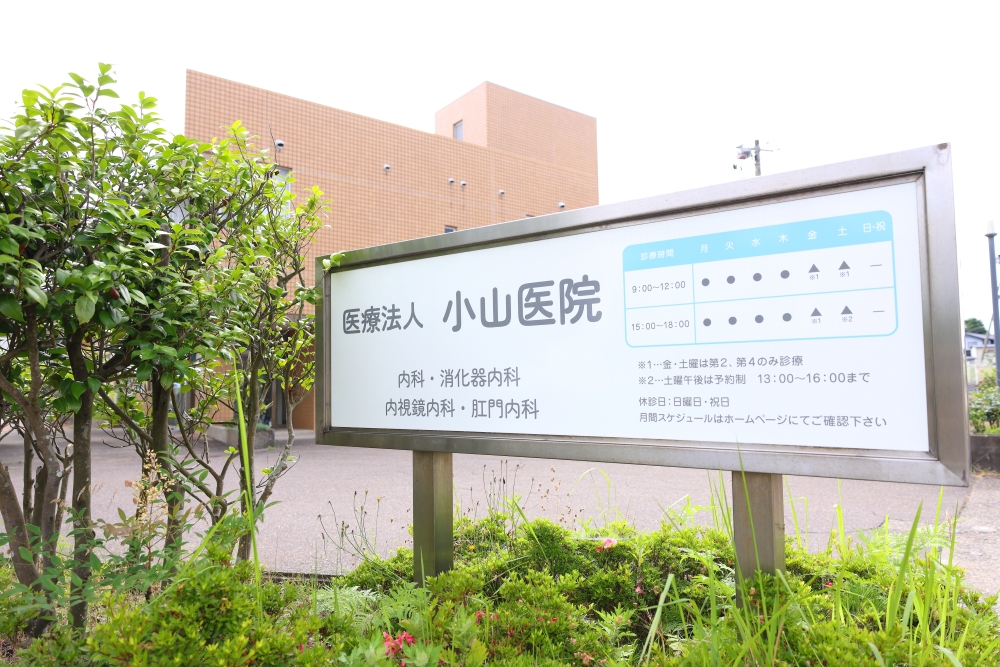 下痢は、何らかの疾患が原因となっていることがあり、下痢が続くなどの場合は原因を特定して適切な治療を受けることが必要です。下痢症状が解消されることで、生活の質(QOL)が大幅に向上します。
下痢は、何らかの疾患が原因となっていることがあり、下痢が続くなどの場合は原因を特定して適切な治療を受けることが必要です。下痢症状が解消されることで、生活の質(QOL)が大幅に向上します。
当院では問診や検査により下痢の原因を突き止め、適切な治療により症状の解消をサポートしています。下痢により生活に支障が及んでいるなど、お悩みの方は当院までお気軽にご相談ください。