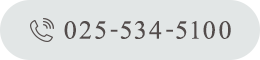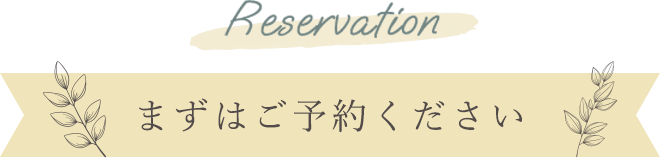過敏性腸症候群とは?
ストレスが原因?

過敏性腸症候群とは、消化器に器質的異常がないにもかかわらず、腹部の不快感や腹痛に伴って便秘や下痢などの便通異常を繰り返す疾患です。命を落とすような重篤な疾患ではないものの、「トイレのない電車やバスなどの空間にずっといられない」など生活の質の大幅な低下を招きます。
現在のところ原因は明確にはなっていませんが、近年研究が進んでおり、ストレスに晒されることで脳下垂体からストレスホルモンが分泌され、このホルモンに刺激により消化管の機能が低下して症状が起こるのではないかと考えられています。
また、大腸などの消化管の蠕動運動の異常、生活習慣の乱れなども関係しているのではないかとも言われています。
どんな人が過敏性腸症候群に
なりやすい?
消化管の機能は自律神経によって制御されているため、ストレスやうつ、喫煙などがリスク要因となることが判明しています。また、性格も関係しており、神経質な性格の方は過敏性腸症候群を発症しやすいと言われています。発症・悪化を防ぐには、ストレスとなるものを回避し、ストレスが溜まったら発散することが大切です。また、喫煙や飲酒もなるべく控え、習慣的に運動に取り組み、十分に休息・睡眠を取ることも心がけましょう。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群では、以下のような症状を示します。
- 腹部の不快感や痛みが数週間~数ヶ月にわたって続く
- 数ヶ月にわたって便秘と下痢が続く
- 排便をすると一時的に腹痛が解消する
- 形状が崩れた便が出るようになる
- 排便回数が乱れる
- 排便後も、便を出し切れていない感覚を覚える
- ストレスに晒されると症状が増悪する
過敏性腸症候群の種類
過敏性腸症候群は、症状に応じて下痢型・便秘型・混合型に分類されます。
下痢型
比較的若年の男性に多いと言われています。激しい腹痛とともに下痢が1日に3回以上発生します。症状は突然発生するため外出が億劫になりますが、それにストレスを感じて症状が増悪するケースも多いです。
便秘型
女性に好発します。腸管が痙攣することで便が腸内に滞留します。排便時に腹痛が起こり、強くいきまないと排便できなくなり、便はウサギの糞便のようなコロコロした形状になります。また、排便後も便が残っている感覚を覚えます。
混合型
激しい腹痛とともに便秘と下痢が繰り返し起こります。
過敏性腸症候群の検査
 過敏性腸症候群で起こる症状は、潰瘍性大腸炎や大腸がんなど他の消化器疾患でも現れます。そのため、大腸カメラ検査などにより除外診断を行います。
過敏性腸症候群で起こる症状は、潰瘍性大腸炎や大腸がんなど他の消化器疾患でも現れます。そのため、大腸カメラ検査などにより除外診断を行います。
当院では、鎮静剤を使用し、苦痛を最小限に抑えた大腸カメラ検査を実施しています。不安な症状などがあれば、お気軽に当院までご相談ください。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群の治療では、生活習慣の改善と薬物療法を実施します。
生活習慣の改善
最初に問診を行い、生活習慣を詳しくお聞きします。過度なストレスや疲労、睡眠不足などにお悩みの場合、改善に向けて適切なアドバイスを行います。
また、普段からアルコールや香辛料を過剰摂取している場合、症状の増悪を招く恐れがあるため、摂取量を減らすことが必要です。
その他、以下を意識しましょう。
- 喫煙者の方は、治療をきっかけに喫煙に取り組みましょう。
- キノコ類や海藻類、バナナなど食物繊維が豊富な食品を意識して摂りましょう。特に、便秘型の方では、腸内環境を改善する乳酸菌を含む食品を食べることが推奨されます。
- 下痢型の方は脱水の恐れがあるため、適宜水分補給を行ってください。なお、冷たい飲み物は胃の負担となるため、なるべく常温あるいは暖かい飲み物を飲みましょう。
- 適度に運動を行うことでストレス解消が期待できます。激しい運動は必要なく、軽いウォーキングを習慣的に行いましょう。
薬物療法
生活習慣の改善を行っても効果が不十分な場合、薬物療法も開始します。お薬は、過敏性腸症候群のタイプや患者様の症状に応じて適切なものを処方します。
過敏性腸症候群の食事
(低FODMAP食)

近年の研究より、食事内容によって過敏性腸症候群の症状の悪化を招くことが判明してきました。
FODMAPとは、発酵性(Fermentable)、オリゴ糖(Oligosaccharides)、二糖類(Disaccharides)、単糖類(Monosaccharides)、ポリオール(Polyols)の5つの英語の頭文字を取ったもので、小腸で吸収されにくく大腸で発酵しやすい特徴があります。FODMAPを豊富に含む「高FODMAP食」を過剰摂取した方に、症状の増悪が認められたというデータが出ています。そのため、過敏性腸症候群の患者様は普段の食生活を見直し、「高FODMAP食」を食べ過ぎていないか確認しましょう。
高FODMAP食の摂取量を制限して低FODMAP食(FODMAPが少ない食品)を意識して食べるようにし、食事内容と腹部の症状の変化を日記につけましょう。症状が良くならない場合は食事日記を確認し、高FODMAP食品の摂取を制限できているか見直してください。それでも症状が改善しない場合は、原因がFODMAPの他にあると考えられます。
以下は、低FODMAP食と高FODMAP食の主な食品例です。
低FODMAP食
- 米、玄米、十割蕎麦、フォー、ビーフン
- 牛肉、豚肉、鶏肉、魚、卵
- ホウレンソウ、カボチャ、トマト、ジャガイモ、ダイコンなどの野菜
- 木綿豆腐
- マーガリン、バター
- メープルシロップ
- 紅茶、緑茶
高FODMAP食
- パン、うどん、ラーメン、パスタなどの小麦を使った食品
- アスパラガス、たまねぎ、長ネギ、ニラ、サツマイモなどの野菜
- 納豆、大豆、豆乳
- ソーセージ
- はちみつ
- アイスクリーム、チョコレート
- 牛乳、ヨーグルト
- ウーロン茶
実践方法
1高FODMAP食を減らす(4~6週間)
治療開始から4~6週間は、高FODMAP食を食べるのを制限してください。
この期間が終わった頃に症状が良くなっているか確認します。症状の改善が認められる場合、過敏性腸症候群の原因が高FODMAP食であったと考えられます。
なお、症状が改善しなかった場合は、過敏性腸症候群の原因がFODMAPの他に考えられます。
2高FODMAP食を少しずつ試していく(6週間後~)
この期間は、数ある高FODMAP食品のうち、何が原因となっているか確認します。
制限していた高FODMAP食を1つずつ口にし、食べても症状が起きない場合、その食品は原因ではないと判断されます。
3原因の高FODMAP食を省いて食事を摂る
原因となる食品が分かれば、該当食品を除いた食事を摂りましょう。
原因となる食品が多数ある場合、栄養バランスが偏ってしまいかねないので、他の食品で栄養バランスを整えましょう。