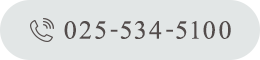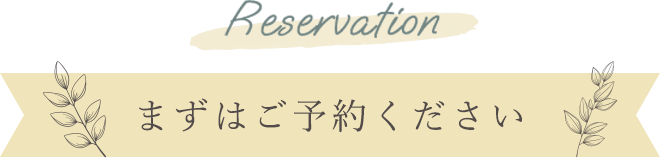胃もたれとは?どんな感覚?

胃もたれとは、胃の中に食物が残っているように感じる症状です。日頃からよく起こる症状であり、「胃が何となく重く感じる」「胃にずっと食べ物が留まっている感覚がある」と訴えることが多く、胃もたれから吐き気を催すこともあります。
食べ過ぎによる胃もたれは数時間経過すると解消します。そのため、胃もたれが持続している場合、「胃薬を飲んでおけば、すぐ解消するだろう」と軽視されることが多いですが、なかには胃がんなど深刻な疾患の症状として起きていることもあります。長期間にわたり続く場合は一度当院までご相談ください。
胃もたれの症状
胃もたれの感じ方には個人差があり、「胃が重苦しい」「胃が張る」「胃がむかつく」などと表現されます。
また、胃もたれと似た症状に「胸焼け」があります。症状が起こる部位や持続期間などに違いがあり、胃もたれは胃の不快感が長時間持続する一方、胸焼けはみぞおちの辺りからのどにかけて、ヒリヒリ・ジリジリした不快感が一時的に起こります。胸焼け症状がみぞおち周辺やのどに症状が現れるのは、胃酸を含む胃の内容物が食増に逆流し、食道粘膜に炎症が発生するからです。
胃もたれの原因
胃は、私たち人間が生活していくために非常に重要な働きをしています。
胃もたれは、胃機能が低下することで起こる症状の1つです。
- 逆流性食道炎
- 機能性ディスペプシア
- 萎縮性胃炎
- 慢性胃炎
- ピロリ感染
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 胃がん
- 食道がん
上記は胃もたれを起こす内的要因です。一方、外的要因には暴飲暴食、高脂肪食の過剰摂取、早食いなどが挙げられます。他にも、ガムを噛むことが多かったり、炭酸飲料を大量に飲んだりすることで、胃の中に大量の空気が流れ込み、胃もたれを引き起こしてしまいます。
また、外的要因は食事だけに限らず、睡眠不足やストレスも要因となります。胃機能は自律神経によって制御されており、睡眠不足やストレスから自律神経が乱れると、胃腸機能が低下し、胃もたれが起こることがあります。昨今は健康志向の方が増えてきていますが、生活リズムや環境にも気を付けましょう。
上記で胃もたれの原因疾患を羅列しましたが、このうち「機能性ディスペプシア」については消化器系に器質的な異常がないにもかかわらず、消化器症状を引き起こします。近年研究が進められ、ストレスやピロリ菌感染など複数の要因が絡み合って起こると分かりました。
胃もたれの検査
 暴飲暴食後に起こる胃もたれはよくあることで、深刻に受け止める方は少ないでしょう。しかし、「胃薬を飲んだにもかかわらず解消しない」など症状が持続する場合、消化器系の疾患が原因となっている可能性があり、医療機関で検査を受けることが推奨されます。
暴飲暴食後に起こる胃もたれはよくあることで、深刻に受け止める方は少ないでしょう。しかし、「胃薬を飲んだにもかかわらず解消しない」など症状が持続する場合、消化器系の疾患が原因となっている可能性があり、医療機関で検査を受けることが推奨されます。
胃もたれの検査には胃カメラ検査を行います。検査によりピロリ菌の感染の可能性が考えられる場合、追加で判定検査を行います。
胃もたれの解消
胃カメラ検査を行って異常が発見されなかった場合、胃もたれの症状が続いていたとしても薬物療法をいきなり行わず、食生活など生活習慣の改善に取り組んでいきます。
日常生活では以下を意識しましょう。
- 食事はしっかり噛むようにする
- 高脂肪食や胃を刺激する食べ物は少なくし、野菜が多いバランスの整った食事を摂る
- お腹いっぱいまで食べず、腹八分目に抑える
- 睡眠をしっかり取る
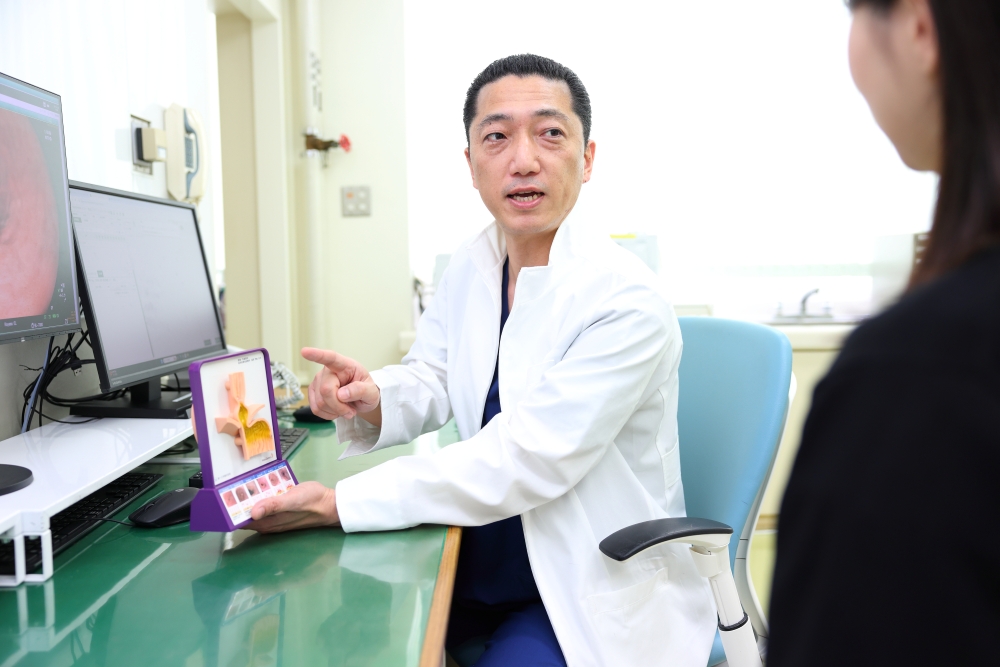 機能性ディスペプシアが原因と診断された場合は、生活習慣の改善とともに胃の運動機能を向上させる薬物療法を行います。
機能性ディスペプシアが原因と診断された場合は、生活習慣の改善とともに胃の運動機能を向上させる薬物療法を行います。
その他、胃カメラ検査により疾患が発見された場合、早期改善に向けて治療に取り組みましょう。急性胃炎や胃潰瘍であれば胃酸分泌抑制剤を使用し、ピロリ菌陽性となった場合は除菌治療を行います。
胃もたれが長期間続くのはしんどいと思いますが、胃腸機能を改善させるきっかけと考え、前向きに治療に取り組みましょう。
胃もたれの時はどんな体勢がいい?
右側臥位(身体の右側を下にして横になった状態)で寝ると消化が促されます。仰向けの状態では消化された食物が胃に留まってしまうため、胃もたれが起きている場合は右側臥位で5分以上寝るようにしましょう。
なお、消化にかかる時間は胃の形状によっても異なり、消化しきるまでに8時間ほどかかる方もいます。特に、胃の上部が変形した「瀑状胃(ばくじょうい)」では、胃の上部に食物が留まりやすく、胃酸が過剰に分泌されてしまうため、胃炎のリスクが高い状態です。日本人では10人中2~3人に認められます。
胃の検診で瀑状胃が認められた場合、食後は左側臥位で寝て、その後はうつ伏せになり、最終的には右側臥位で寝ると、消化と消化物の移動がスムーズになります。