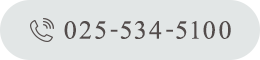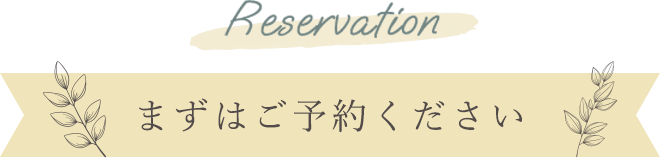初めての方へ
初診時にお持ち頂くもの
- マイナンバーカード(健康保険証)
- お薬手帳
- 他の医療機関からの紹介状 ※お持ちの方のみ
- 高齢者受給者証 ※お持ちの方のみ
- 乳幼児・小児医療証(子ども医療費の助成)※お持ちの方のみ
ご受診にあたっての
注意事項
- 初診、および月初めの受診の際は、マイナンバーカード(健康保険証、コピーは不可)をお持ちください。
- 就職・転職などにより、ご加入になっている健康保険が変わった際は、新しい保険証を受付にご提示ください。
- 住所や電話番号など保険証の内容に変更が入った際は、受付にお知らせください。
- 受給者証(老人・身障医療等)をお持ちの方はマイナンバーカード(健康保険証)と一緒にお出しください。
- 妊娠中、および妊娠の可能性がある方は、必ずお申し出ください。
- ひどい痛みや高熱、嘔吐などの症状がある場合は、受付にお申し出ください。
- 現病歴(いつ頃から、どんな症状が現れているのか)や既往歴(今までに罹った主な病気)、処方箋の内容、喫煙、飲酒、また健(検)診結果などについてもお教え頂くと、診察がスムーズに進みます。
- 個人情報の取り扱いにはスタッフ一同、細心の注意を払っておりますので、安心してご受診ください。
受診時の流れ
1予約
当院では、待ち時間をできるだけ減らすために予約優先の診療を基本にしています。
電話予約、ネット予約が可能であり、枠に空きがある場合には当日予約もできます。ご来院の際には事前の予約をお願いします。ただし、ご予約が無くご来院いただいた場合も少しお待ちいただければ対応可能です。
2受付
 当日は余裕をもって10分前にはお越しください。
当日は余裕をもって10分前にはお越しください。
受付にてマイナンバーカード(健康保険証)、あれば診察券、紹介状、お薬手帳をご提出ください。
また、受付時に問診表をお渡しいたしますので、必要事項を全てご記入ください。
ご不明な点はお気軽に受付にご質問ください。
3待合室
順番が来るまでお待ちください。また、緊急性の高い患者様がおられる際は順番を変更させて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
4診察
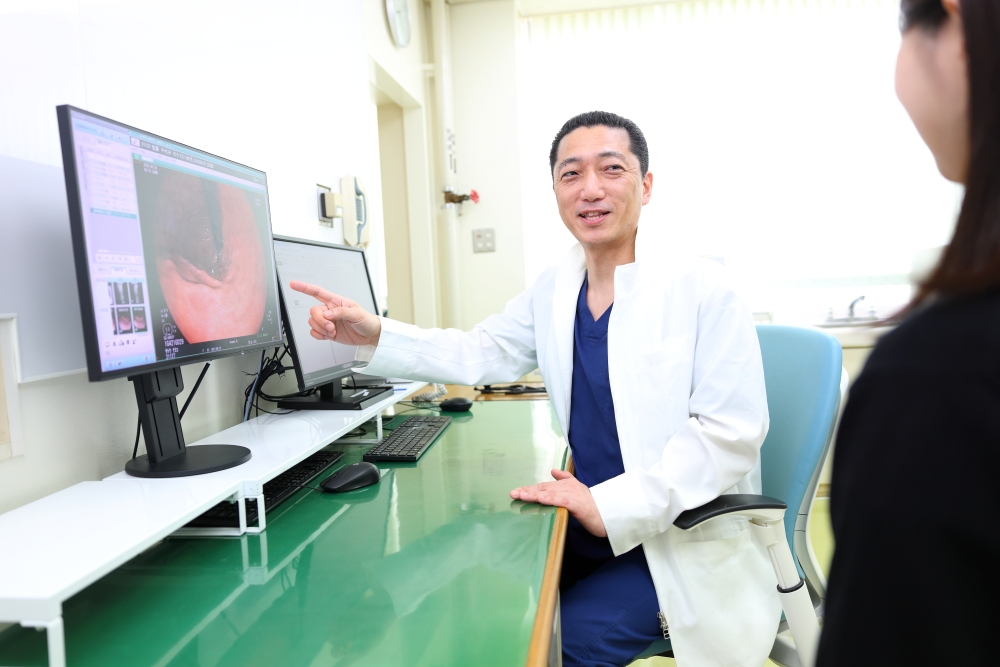 問診票にご記入頂いた内容をもとに、医師が診断・治療方法のご説明をいたします。
問診票にご記入頂いた内容をもとに、医師が診断・治療方法のご説明をいたします。
治療に対するご希望、ご質問などもお聞きしますので、遠慮なくお伝えください。
また、この時に必要に応じて検査なども行います。
レントゲンの検査が入ることがあります。着替えやすい服装でお越し下さい。
5お会計
診察、処置後は待合室でお待ちください。
受付でお名前をお呼びしますので、お会計をお願いいたします。
お薬が出ている場合は院外処方箋をお渡しいたします。
当院の感染症対策に
ご協力ください
当院は発熱等の症状がある方が、適切に診療・検査を受けられる施設「外来対応医療機関」に指定されております。
当面は「時間的分離(予約制)」「空間的分離(別入口、別診療室、車待機)」を継続するため予め予約をお願いしております。また診察の前後に医院の外(ご自身のお車内)でお待ちいただきますので、可能な限りお車でご来院ください。お手数ですが御協力のほどよろしくお願いいたします。
診療案内
(外来・保険診療)
内科
内科は、内科系の症状・疾患を対象とした診療科で、「何となく体調が悪い」「どの診療科を受診すべきか分からない」「症状は軽いが不安」などの場合、当院の内科までお気軽にご相談ください。風邪やインフルエンザ、腹痛などの消化器症状、胸痛や動悸などの肺・循環器症状、生活習慣病、慢性疾患まで様々な疾患・症状に対応しています。また、専門的な検査・治療が必要な場合、適切な診療科にご案内しています。
発熱や感染症の症状がある
患者様へ
咳や発熱などの症状が出ている場合、新型コロナウイルスなどの感染症の可能性があります。他の患者様や当院スタッフへの感染リスクを抑えるため、これら症状が出ている場合はお越し頂く前にお電話をお願いします。スタッフより受診方法などについてご説明させて頂きます。
消化器内科(内視鏡内科)
 消化器内科では、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸などの消化管、膵臓・肝臓・胆のうなどの消化をサポートする付属器官に起こる症状・疾患を対象とした診療科です。
消化器内科では、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸などの消化管、膵臓・肝臓・胆のうなどの消化をサポートする付属器官に起こる症状・疾患を対象とした診療科です。
当院の消化器内科で相談されることが多い症状には、腹痛や吐き気・嘔吐、便秘、下痢などが挙げられます。これら症状は一時的なものであることが多いですが、なかには深刻な疾患が原因となっていることもあります。そのため、診察時点では様々な可能性を考慮し、必要に応じてレントゲン検査、血液検査、胃カメラ検査、大腸カメラ検査などを行います。
肛門科
肛門科で対応する疾患は多岐にわたりますが、特に多いのが痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)です。痔は進行していない段階では生活習慣の見直しや薬物療法により治療可能ですが、デリケートな部分のため受診を躊躇する方も多いです。しかし、医療技術の進歩により、悪化した場合も従来に比べて容易に治せるようになり、仕上がりも綺麗にすることができるようになりました。
当院では、安心して受診して頂くため、患者様のプライバシーに配慮した環境を整えています。肛門科以外の診療科も設置しており、受付にて肛門部の治療についてお話しすることはないため、他の方に知られるリスクもありません。安心してご相談ください。
予防接種
 予防接種とは、いわゆるワクチン接種のことをいいます。ワクチンとは、病原体(細菌、ウイルス など)の病原性を極限まで弱めた生ワクチン、無力化した病原体を集めた不活化ワクチンなどがあるのですが、これらを体内に接種することで、特定の感染症に対する免疫が自然感染でなくともつけられるようになるというものです。そして接種後に同様の病原体が体内に侵入したとしても発症しにくくなる、発症しても軽度で済むので重症化のリスクが減少するという効果が期待できるようになります。
予防接種とは、いわゆるワクチン接種のことをいいます。ワクチンとは、病原体(細菌、ウイルス など)の病原性を極限まで弱めた生ワクチン、無力化した病原体を集めた不活化ワクチンなどがあるのですが、これらを体内に接種することで、特定の感染症に対する免疫が自然感染でなくともつけられるようになるというものです。そして接種後に同様の病原体が体内に侵入したとしても発症しにくくなる、発症しても軽度で済むので重症化のリスクが減少するという効果が期待できるようになります。
なお、予防接種は単に個人の身を守るというだけでなく、ワクチンを打つことができない方たちの身も守るということにもなるので、集団免疫を高めることにもつながります。つまり市中感染を防ぎ、流行が起きにくい環境が作られるということでもありますので、そのような点からも接種する意義はあります。
当院で行える予防接種
- 新型コロナワクチン
- インフルエンザワクチン
- 肺炎球菌ワクチン
- 四種混合ワクチン(DPT-IPV)
- 三種混合ワクチン(DPT)
- 二種混合ワクチン
- ポリオワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 子宮頚がん予防ワクチン
- 水痘ワクチン
健康診断
- 特定健康診査(特定健診)
- 企業健診(雇入時の健康診断、定期健康診断)
- 人間ドック
健康診断は、ご自身の健康状態を把握し、健康維持や増進に繋げる目的、そして疾患の早期発見・早期治療を目的があります。特に、生活習慣病は自覚症状が乏しく、治療せずにいると深刻な状態になる可能性があります。定期的に健康診断を受け、健康管理に役立てましょう。
自費診療
公的な医療保険が適用されない医療行為のことを自費診療と言います。この場合、治療費の全額が患者様のご負担となります。
当院で行っている自費診療は以下の通りです。
ED(勃起不全)
「Erectile Dysfunction」の略称がEDです。これは日本語で言うところの勃起障害になります。具体的には、満足な性行為が行えるほど勃起力が十分でない、勃起はするもののそれを維持することが困難、勃起をするまでに時間がかかるなどの状態を言います。
なお、EDの原因はひとつではありませんが、大きくは心理的要因(心因性ED)と器質的要因(器質性ED)に分類され、この2つが組み合わさって起きる場合もあります(混合性ED)。心因性EDとは、精神的なストレス、不安、パートナーとのトラブル、性交に関するトラウマ、うつ病などによって引き起こされるEDです。一方の器質性EDは、勃起に関係する神経(脳、脊髄、末梢神経)に障害がある、血管障害(加齢や生活習慣病による動脈硬化 等)によるもの、内分泌機能(テストステロン 等)の低下、陰茎に何らかの異常があるといったことが原因になります。なお混合性EDに関しては、上記二つが関係して発症しているEDです。
EDの治療
ED治療の基本はPDE5阻害薬による薬物療法になります。PDE5阻害薬には種類がいくつかありますが、当院では、バイアグラ、シアリス等を取り扱っています。ただこれらのお薬というのは、作用時間などが異なるものの、いずれも一時的に勃起を持続させる効果があるとされるもので、完治が目的の治療ではありません。
副作用
PDE5阻害薬(バイアグラ、シアリス 等)の使用による副作用ですが、まず狭心症などで使用するニトロ製剤との同時使用は禁忌とされています。副作用に関しては、ほてりや頭痛のほか、バイアグラではめまいや高血圧、シアリスでは消化不良、鼻づまり、紅潮、背部痛などがみられることがあります。ただ、これらのお薬は毎日服用するものではないので、作用時間が終われば解消するようになります。したがって、一過性の場合がほとんどです。
なお、EDの原因が特定し、治療が可能ということであれば原疾患に対する治療をしていきます。また心因性EDであれば、カウンセリングや心理療法による治療などが行われることもあります。
ED治療の料金(税込)
お電話でお問い合わせください。
AGA
AGAは、Androgenetic Alopeciaの略称で、日本語にすると男性型脱毛症になります。これは男性ホルモン(アンドロゲン)が関係しているとされ、主にアンドロゲンに含まれるジヒドロテストステロン(DHT)が主に毛周期(ヘアサイクル)の成長期間を短くさせてしまうというのが原因といわれています。これによって、太く長い毛に生え変わることはなく、どんどん細く短い毛に生え変わるようになっていきます。やがて前頭部や頭頂部は軟毛化し、最終的にはこれらの部分の毛は無くなっていくというのがAGAです。
発症に関しては、思春期を過ぎた頃から始まりますが、進行の程度は個人差があります。多くは、ゆっくり時間をかけて進行し、その大半は30歳を過ぎた頃から目立っていきます。ちなみに日本人の成人男性の4人に1人はAGAを発症しているといわれています。
AGAの治療
当院は、AGAの患者様に対して、AGA治療薬(プロペシア、サガーロ)による処方を行っています。
AGAの発症原因とされるDHTというのは、男性ホルモン(アンドロゲン)の一種であるテストステロンが5α還元酵素と結びつくことでDHTに返還します。ちなみにプロペシアの主成分はデュタステリド、サガーロの主成分はフィナステリドとなっていますが、どちらも5α還元酵素を阻害する働きをする5α還元酵素阻害薬で、DHTの生成を抑制するようになります。5α還元酵素にはⅠ型とⅡ型がありますが、プロペシアはⅡ型のみ、サガーロはⅠ型とⅡ型に作用すると言われています。そのため、サガーロの方が発毛効果は高いと言われていますが、実際に臨床試験の結果、プロペシアと比べてサガーロは約1.6倍の発毛効果があるというデータもあります。どちらを処方するかに関しては、患者様の適正などもみながら判断していきます。服用方法は、両方とも1日一錠となります。
副作用
副作用につきましては、サガーロでは男性機能の不全(勃起不全、性欲減退 など)や肝機能障害、乳房の女性化などが挙げられます。プロペシアでも男性機能不全や肝機能障害等がみられることがあるといわれています。
AGA治療の料金(税込)
お電話でお問い合わせください。
各種抗体検査
当院では、以下の各種抗体検査を自費にて行います。抗体検査とは、ある特定の感染症に対して、被験者(検査を受けられる)の方が、その発症や重症化を防げる免疫があるかどうかを確かめるための検査(血液検査)となります。
具体的には、A型、B型、C型肝炎をはじめ、風疹、麻疹、おたふく、水痘といった各種抗体検査を行っています。なかには幼少期に上記で挙げた病気を予防するワクチン接種を受けたという方がいるかもしれません。ただ、接種時に抗体が十分につかなかった、あるいは接種から長い時間が経過して、抗体そのものが低下してきているということも考えられます。このような可能性を確認するためにも一度これらの抗体価を調べ、その結果として抗体が不十分ということになれば、ワクチン接種を受けるようにしましょう。
各種抗体検査の料金(税込)
お電話でお問い合わせください。
アレルギー検査
ご自身がアレルギー体質であるかどうか、またアレルギーの原因が何かを調べるために行う検査をアレルギー検査といいます。どちらも血液検査となりますが、前者を非特異的IgE検査、後者を特異的IgE検査といいます。
非特異的IgE検査では、1型アレルギー反応と深く関わっているとされる血液中に存在するIgE抗体を測定していきます。これによって、同検査を受けた方のアレルギー体質の有無が判定できるようになります。一方の特異的IgE検査は、アレルギー反応(鼻水、くしゃみ、ぜんそく、じんま疹 等)の原因(アレルゲン:アレルギーの原因となる物質)が何かを調べる検査になります。例えば、アレルゲンが特定できないという場合に行われるView39検査も特異的IgE検査のひとつです。これによって、39種類のアレルゲン(ペット、ダニ、カビ、樹木、花粉、食物 など)を一度に検査することができます。
訪問診療
当院は、外来での通院が困難とされる患者様を対象に訪問診療も行っています。訪問診療とは、ご自宅や介護施設といった場所で過ごしている患者様の元へ医師や看護師などの医療従事者が訪問することで、外来時の診療と同等の診察、検査、治療が受けられるようになります。具体的には、血液検査をはじめ、点滴や注射などの処置も受けることもできます。また処方箋も発行し、後日薬剤師が訪問する、あるいは訪問診療時に同行するといったことも可能です。
訪問診療を希望される場合は、当院とご契約して頂く必要があります。訪問診療を利用されている患者様は、以下のような症状がみられる方になります。なお、対象になる条件として、年齢や症状の程度は関係ありませんので、ご希望の方はいつでもご相談ください。
訪問診療の対象となる
患者様(例)
- 患者様ご自身での通院が困難な方(認知症の患者様も含む)
- 退院後、ご自宅での治療が引き続き必要な方
- 医師による定期的な診療が必要な方
- 主治医が決まっていない方
など
往診について
当院と訪問診療のご契約をされると診療の開始となり、基本的には事前にスケジュールを立て、月1~2回の間隔で医師が訪問することになります。ただ、体調が急変したなどの理由から訪問日でない日に医師がかけつけて患者様に医療行為を行うこともあります。これを往診と言いますが、当院でも往診については24時間365日対応しています。
訪問エリアについて
訪問エリアに関しましては、当院から半径16kmの範囲としています。
ご自宅がその範囲内にあるか分からないなど、詳細につきましてはお問い合わせください。
料金について
訪問診療は、保険診療の適用範囲となります。そのため健康保険で支払う一部負担金がその費用となります。高額負担となっても保険診療ですので、高額療養費(高額医療費支給制度)が適用され、申請することで、高額分に関しては払い戻されるようになります。
また、介護保険でのご利用となれば、居宅療養管理指導料がかかります。そのほか、お薬代は院外処方となるので別途費用となります。上記以外にも、交通費(往診の場合)や包帯やガーゼなどの材料費をご請求させて頂くこともあります。
お問い合わせはお気軽に
契約を希望する場合はもちろんですが、訪問診療について聞きたいことがある場合も遠慮なく、ご連絡ください。受付時間内であれば、受付スタッフが対応いたします。診察内容、費用に関すること、訪問診療の範囲など、気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。