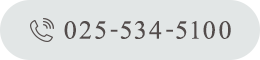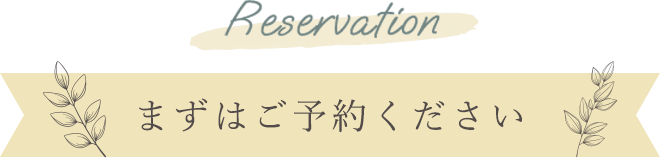ピロリ菌がいると
どんな症状が出る?
ピロリ菌に感染した場合、胃炎などの消化器疾患が発生する可能性があります。
以下は、ピロリ菌感染が原因となる疾患別の主な症状です。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍・
胃がんなどが発生した場合
炎症が慢性化することで、胃潰瘍・十二指腸潰瘍に至った場合は以下のような症状が起こります。
- 心窩部痛(胃潰瘍の場合は食事中や食後、十二指腸潰瘍の場合は空腹時や夜間)
- 胃痛
- 胸焼け
- 食欲不振
胃がんにかかって
しまった場合
胃がんは初期では自覚症状が乏しいですが、進行すると以下のような症状を示します。
- 早期膨満感
- 腹痛
- 吐き気・嘔吐
- 体重減少
- 貧血
ピロリ菌とは
 一般的にはピロリ菌と呼ばれている細菌(微生物)の正式名称はヘリコバクター・ピロリです。これは胃の中に生息する4ミクロン(4/1000mm)程度の大きさになります。
一般的にはピロリ菌と呼ばれている細菌(微生物)の正式名称はヘリコバクター・ピロリです。これは胃の中に生息する4ミクロン(4/1000mm)程度の大きさになります。
胃の中は酸性下にあるので、細菌などの生物が生息し続けるには厳しい環境にあります。そのような状況下ではありますが、ピロリ菌は胃の中がそれほど酸性下にない幼少期の胃に侵入し、胃内にある尿素を自らが分泌する酵素(ウレアーゼ)によって、アンモニアと二酸化炭素に分解します。これによって胃酸をアンモニアで中和させられるようになるので、成長して厳しい酸性下になった後でもピロリ菌は生きながらえるようになるのです。
ピロリ菌に関係する病気
ピロリ菌に感染したとしても、何らかの影響がすぐに現れることはありませんがやがて胃炎(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)を発症させ、それが胃粘膜の委縮を招き、その結果、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気を発症させる原因にもなります。そのため、ピロリ菌感染が疑われる場合は、速やかにピロリ菌検査を受けるようにしてください。
ピロリ菌の感染経路
感染経路に関しては、完全に特定していませんが、衛生環境がしっかり整っていない頃は井戸水から感染することもありました。ただ現在はピロリ菌に感染している成人(保護者など)から主に食べ物の口移しによって感染するとされる家庭内感染が疑われています。
ピロリ菌の検査
 ピロリ菌感染の有無を調べる検査には、採血や採尿で抗体(ピロリ菌に対する)の有無を調べる抗体測定法、便中に含まれる抗原(ピロリ菌)の有無を調べる抗原測定法、特殊な検査薬を服用後に呼気中に含まれる二酸化炭素の量を調べることで感染の有無を判定する尿素呼気試験法というのがあります。また、上部内視鏡(胃カメラ)を用いて組織の一部を採取し、それを詳細に調べることで感染の有無を判定する検査(培養法、迅速ウレアーゼ法、組織鏡検法)もあります。
ピロリ菌感染の有無を調べる検査には、採血や採尿で抗体(ピロリ菌に対する)の有無を調べる抗体測定法、便中に含まれる抗原(ピロリ菌)の有無を調べる抗原測定法、特殊な検査薬を服用後に呼気中に含まれる二酸化炭素の量を調べることで感染の有無を判定する尿素呼気試験法というのがあります。また、上部内視鏡(胃カメラ)を用いて組織の一部を採取し、それを詳細に調べることで感染の有無を判定する検査(培養法、迅速ウレアーゼ法、組織鏡検法)もあります。
ピロリ菌の除菌
検査結果からピロリ菌の感染が確認されると除菌治療が必要となります。まず3種類のお薬(プロトポンプ阻害薬、クラリスロマイシン、アモキシシリン)を1日2回(朝夕)の割合で服用していくのですが、1週間(7日間)限定で行います(一次除菌)。そして服用を終えた日から数ヶ月後に除菌判定検査をします。
その結果、除菌できてないことが確認されると、二次除菌が行われます。一次除菌と同様に3種類のお薬を1週間限定で1日2回の頻度で服用していきます。二次除菌では、クラリスロマイシンをメトロニダールというお薬に変更します。その後、服用が終了した日から1ヶ月後に再び除菌検査を行います。なお除菌率に関しては、一次除菌が70%程度、二次除菌が90%程度と言われています。
二次除菌でも効果がなかったという場合は、三次除菌ということも可能ですが、この場合は保険適用外による除菌治療となります。
除菌治療の注意点
事前確認
以下に1つでも該当する場合、主治医に事前にお伝えください。
- 風邪薬や抗菌薬で何らかの副作用が起こったことがある
- お薬の服用によりアレルギー症状が起こったことがある。
- ペニシリンなどの抗菌薬を飲んだ際、ショックなど深刻なアレルギー症状が起こったことがある。
治療中の注意
- 医師の指示にしたがって、服用を続けてください。
- 自己判断により服用を中断した場合、ピロリ菌がお薬に耐性を持ってしまう可能性があります。
- 二次除菌を行っている間は、お酒を飲むことはお控えください。
副作用
除菌治療薬を服用することで、副作用として下痢などの消化器症状、味覚障害、発疹が生じる可能性があります。症状に応じて以下の対応を取ってください。
軟便、軽い下痢などの消化器症状や
味覚障害が起きた場合
ご自身の判断により減薬することは控え、当初医師から指示があった通り服用を続けましょう。なお、症状が強くなっている場合、当院までご相談ください。
発熱や腹痛を伴う下痢、下痢に
粘膜や血液が混ざっている場合、
または発疹の場合
すぐに服用をストップし、当院までご連絡ください。また、他に不安な症状などがあれば、当院までお気軽にご相談ください。