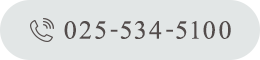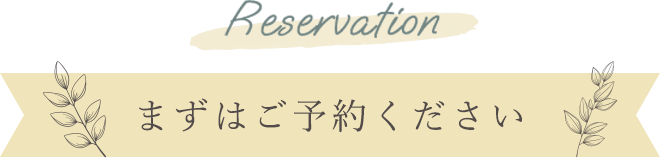腹部膨満感
(お腹がパンパンに張る)

腹部膨満感とは、お腹が張って苦痛を感じる状態です。食べ物を食べるときは空気も一緒に飲み込みますが、その量が多いと膨満感を覚えます。また、便秘などでも感じることがあり、ありふれた症状ですが、なかには深刻な疾患の症状として発生していることもあります。特に、膨満感に伴って激しい腹痛や息苦しさなどの症状が起きている場合、すぐに当院までご相談ください。また、腹痛が繰り返す、体がむくむ、尿量が減る、食欲不振などの症状が膨満感に伴って起きている場合も早めに検査を受けることが推奨されます。げっぷやおならが頻発する、おならや便が数日間出ずに腹部が張っている、食後や睡眠中にお腹が張って苦しいという場合も、一度当院までご相談ください。
腹部膨満感
(お腹がパンパンに張る)で
考えられる病気・原因
便秘
便秘により便が腸内に滞留している場合、腹部膨満感や腹痛などの症状が発生することが多いです。便秘は器質性の疾患が原因となっていることがあるため、便秘が長期間続いている場合は当院まで一度ご相談ください。便秘の原因を問診や検査を行って特定し、適切な治療に繋げます。
腸閉塞
腸閉塞とは、腸管癒着や蠕動運動の低下などが原因となり、内容物が腸内に滞留する状態です。膨満感や腹痛、嘔吐などの症状を示します。重症化すると腹膜炎など深刻な合併症が起こる可能性があるため、これらの症状が起きている場合は早めに当院までご相談ください。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、小腸・大腸に器質的な異常が発見されないにもかかわらず、腹痛や膨満感に伴って、便秘や下痢を繰り返す疾患です。はっきりとした原因は分かっていませんが、過剰なストレス、食生活の乱れ、消化機能の異常など複数の要因が組み合わさることで起こると言われています。治療は、生活習慣の改善と薬物療法を行います。
呑気症
食べ物を食べる際に、空気を大量に飲み込み、胃に空気が蓄積して膨満感が起こります。胃に滞留している空気はおならやげっぷとして排出されます。
逆流性食道炎
逆流性食道炎とは、胃酸など胃の内容物が食道に逆向きに流れ込み、食道粘膜に炎症が発生する疾患です。胸焼けや呑酸、咳などが主な症状ですが、膨満感が発生することもあります。
かつては高齢者に好発する疾患でしたが、近年は食生活が欧米化したことで若年層の発症も目立ってきています。再発しやすい特徴があり、悪化すると食道がんなどに繋がる可能性があるため、早期治療・再発予防が欠かせません。
急性胃腸炎
胃や腸の粘膜に起こる急性の炎症で、ウイルスや細菌などの病原体の感染、お薬の副作用などが原因となります。腹痛や下痢、吐き気・嘔吐などが主な症状ですが、膨満感や食欲不振、発熱などの症状が起こることもあります。
機能性ディスペプシア
消化管粘膜に炎症など器質的な異常がないにもかかわらず、胃の不快感や胃もたれ、膨満感、早期膨満感、心窩部痛などの症状が現れます。消化管機能の障害や知覚過敏などが原因と言われています。
上腸間膜動脈症候群
上腸間膜動脈は、腹部大動脈から分岐する血管で、周囲を囲む脂肪がクッションの役割を果たしています。しかし、ダイエットなど急激な体重減少により脂肪が減少した場合、十二指腸が血管によって圧迫され、食後の胃もたれ、腹痛、膨満感、吐き気などの症状が起こります。
体位によって症状が変化し、仰向けの状態で寝ると血管の圧迫が強くなり症状が起こりますが、うつ伏せの状態では圧迫が弱まり症状が軽減します。
腹部膨満感
(お腹がパンパンに張る)を
解消する方法
食生活の改善

腸内環境の乱れにより膨満感が発生することがあります。この場合、腸内環境を改善することにより、腸内のガスや便が体外に排出され、膨満感が落ち着きます。腸内環境を改善するには、ヨーグルトや納豆、漬物、キムチなど善玉菌を豊富に含む食品を食べましょう。
また、カリウムを多く含む食品も腹部膨満感の改善効果が見込めます。カリウムは、体内の水分量を調整する働きがあり、バナナやアボカドに多く含まれています。
ストレスの解消
胃腸機能は自律神経によって制御されています。ストレス過多の生活となっている場合、自律神経が失調し、胃腸機能が弱まることで膨満感が起こることがあります。
ストレスを溜めないように週1回以上は趣味など、リラックスできる時間を作りましょう。
腹部膨満感、
お腹がパンパンに張る
症状は
上越市の小山医院まで
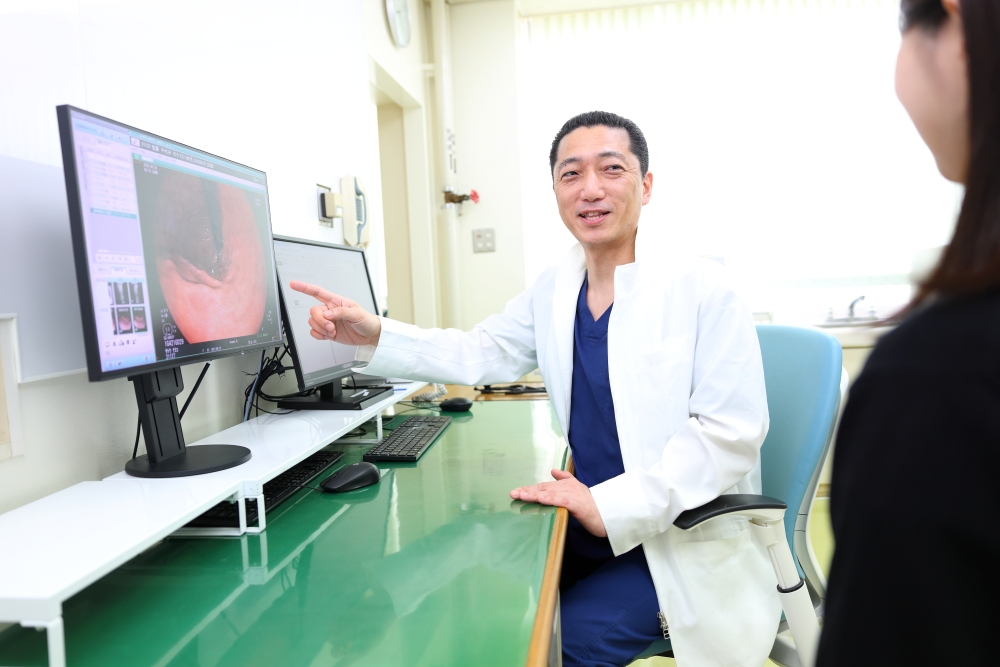 膨満感が長引いている場合、あるいは膨満感に伴って他の症状も起きている場合、何らかの疾患が原因となっていることも考えられるので、上越市大潟区の小山医院までご相談ください。
膨満感が長引いている場合、あるいは膨満感に伴って他の症状も起きている場合、何らかの疾患が原因となっていることも考えられるので、上越市大潟区の小山医院までご相談ください。
当院では、問診や検査にて疾患の有無を調べ、原因に応じた適切な治療を行っています。膨満感は症状を正確に伝えづらい症状ですが、担当医が丁寧に状態をお伺いするので、安心してご相談ください。