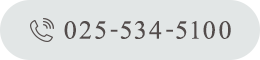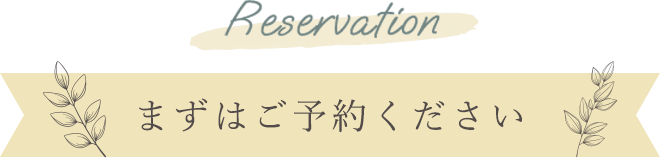体重がどれくらい減ったらやばい?
異常は何キロから?
体重減少について

体重減少は症状名の通り体重が減ることですが、医学的には体重が6ヶ月間で5%以上減少した状態と定義されています。例えば、体重60kgの方が6ヶ月間で3kg以上、80kgの方では4kg以上減った場合、糖尿病などの疾患を発症している可能性があります。
運動や食事制限によるダイエットなどで体重を意図的に落とす分は特に心配はありませんが、BMI25以下の普通体型の方がダイエットに取り組み10%以上体重が減った場合、栄養失調に陥っていることが疑われ、治療が必要になることもあります。20%以上元の体重から減少した場合、栄養障害・多臓器障害などが発生していることが疑われるため、すぐに当院までご相談ください。
脱水でも体重が減る?
食事による摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが崩れ、エネルギーが足りなくなることで体重が減少します。これは、食事を摂取してから消費されるまでの代謝プロセスのどこかで何らかの異常が発生していることで起こります。また、体重2/3は水分が占めているため、水分が過剰に不足した場合、体重が減少します。
ダイエットでない
体重減少は危険
 体重減少が意図的なものなのか、予期せぬものなのかという点は診断する上で注目すべきポイントとなります。ダイエットや糖尿病治療薬の服用などは意図的な体重減少なので、基本的に心配はないですが、神経性無食欲症(拒食症)には注意が必要です。この疾患は、体重が増えることに恐怖心を抱き、過度な食事制限などを行ってしまうため治療が必要です。
体重減少が意図的なものなのか、予期せぬものなのかという点は診断する上で注目すべきポイントとなります。ダイエットや糖尿病治療薬の服用などは意図的な体重減少なので、基本的に心配はないですが、神経性無食欲症(拒食症)には注意が必要です。この疾患は、体重が増えることに恐怖心を抱き、過度な食事制限などを行ってしまうため治療が必要です。
一方、予期せぬ体重減少は何らかの疾患が潜んでいる可能性が高いため、早めに受診しましょう。
体重減少の症状
体重減少を引き起こす疾患は多岐にわたり、体重減少に伴って様々な症状が起こります。
特に、食欲不振の有無は体重減少の原因を考える上で重要な手がかりとなります。
他にも以下のように様々な付随症状が起こりますが、なかには原因疾患特有の症状もあります。
- 口渇、多飲、多尿
- 嚥下障害
- 早期膨満感
- 腹痛
- 頭痛
- 下痢
- 嘔吐
- 食行動の異常(過食など)
- 全身倦怠感
- 意欲減退
- 不安
- 抑うつ
- 不眠
- 発熱
- 血圧上昇
- 動悸
- 発汗過多
- 呼吸困難
また、体重減少の自覚がない患者様もいらっしゃいますが、問診などでお聞きする症状・状態(のどの乾き、発汗過多、動悸、倦怠感、微熱、食事を美味しく感じない、普段来ている服が余るようになった、ベルトをきつく締めるようになったなど)から、体重減少の有無をおおよそ判断できます。
体重減少の原因
体重減少の原因は多岐にわたります。診断にあたって食欲不振の有無が疾患を突き止める上で重要な手がかりとなります。
高齢者の場合、主な原因疾患にはフレイルやサルコペニア、認知症、神経筋疾患、心不全、肺疾患などが挙げられます。
また、疾患の治療のために服用しているお薬によって体重が減ることもあります。
体重減少の検査方法
 まずは問診や身体診察を行い、原因が分からない場合には血液検査や尿検査、胸部レントゲン検査、便潜血検査を行います。
まずは問診や身体診察を行い、原因が分からない場合には血液検査や尿検査、胸部レントゲン検査、便潜血検査を行います。
必要に応じて、可能性のある疾患の確定診断のため、血液検査(特定疾患を評価する項目)、尿検査、胃カメラ検査、大腸カメラ検査などを実施します。
体重減少の治療方法

体重減少は、原因疾患の治療により改善が見込めます。検査の結果、入院を必要とする疾患が原因の場合、連携している高度医療機関にご案内します。
原因が特定できなかった場合、1~3ヶ月ほど経過観察を行い、体重減少の有無や疾患が原因と考えられるような症状の有無などを確認します。
治療は薬物療法のほか、以下のように食事指導も行うことがあります。以下をしっかり取り組むことで、体重減少の改善が期待できます。
- 1回の食事量は少量にし、数回に分けて食べる
- 味覚が低下している場合は食事に香りづけを行う
- 介助者にサポートを受けながら食事を摂る
- 食間にカロリーが高いサプリメントを摂る